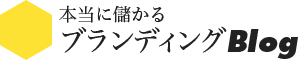何にでも対応できることをウリにしようと、いろいろな事業に手を出しすぎて、そもそも自社が何屋なのかわからなくなってしまう、ブランディングに失敗している企業があります。
そのような状態に陥ると、競争力を失うだけでなく、結局業績を落としてしまうことになります。
この“何屋かわからない”会社が、闇雲に放とうとする商品やサービス・事業のことを、まとめて「よろず屋」と呼びます。
あなたの会社が「よろず屋状態」だとしたら、会社の業績は上がることはありません。
もしくは、今は利益が多少出ていたとしても、すぐに低迷してしまうでしょう。
そこで、なぜ「よろず屋」がダメなのか。その理由をご説明します。

バブル期から現在まで存在する「よろず屋」
かつて多くの日本企業が、「よろず屋」化している時代がありました。
1980年代中ごろのバブル期。
日本の鉄鋼業などの重厚長大企業は、バブルの恩恵で得た有り余るキャッシュを元手に事業を多角化していき、様々な業種のベンチャー企業を立ち上げました。
その一例として、遊園地やスポーツクラブ、リゾート、教育研修、出版、人材派遣、コピーサービス、レストラン、きのこ栽培、巨大迷路、ゴルフ練習場、あわびの養殖、ログハウスなど多くのレジャー施設があります。

しかしバブルの崩壊とともに、いずれの事業も失敗に終わり、この多角化のトレンドは3年で終息したとともに、多額の資金も消えてなくなりました。
売上2000億円を誇る、株式会社ミスミグループ本社の取締役会議長でもある三枝匡(さえぐさ ただし)氏は、当時のそういった企業を「戦略なきよろず屋」と命名したのです。
さすがに現在では、当時のバブル期のような多角化を行う企業はあまり見かけなくなりました。
しかし、違った意味での「よろず屋」が苦境に立たされています。
百貨店と総合スーパーが苦戦する時代
「よろず屋」の例を挙げると、百貨店や総合スーパーも苦戦している企業です。
百貨店は「総合小売り業」と呼ばれ、英語では「General Merchandize Store」略して「GMS」とも呼ばれます。
小売流通業の専門誌『販売革新』(発行:株式会社商業界)によると、百貨店の市場規模は、過去ピーク時の3分の2となる、6兆円まで縮小しています。
2016年から2017年にかけて、「西武春日部店」「西武旭川店」「そごう柏店」「西武筑波店」「西武八尾店」「三越千葉店」「三越多摩センター店」と、百貨店の大量閉店が続きました。
さらに今後も、百貨店の閉鎖が続くと予想されています。
また総合スーパーも、イトーヨーカ堂が2016年度中に20店を閉鎖しました。
同店は2020年度末までに、全店舗の約2割に当たる累計40店を閉鎖し、さらにユニーも「アピタ」「ピアゴ」を2019年2月末までに、合計25店を閉鎖する予定です。

このように百貨店や総合スーパーは、売上に伸び悩み規模を縮小していく傾向にあります。
一方で元気なのは、取扱いカテゴリーを絞りつつ、そのカテゴリーの中で豊富な品揃えを誇る「ユニクロ」「無印良品」「ニトリ」などの専門店です。
また、スーパーのなかでも食品部門に特化している「いなげや」「ライフ」「ヤオコー」などは元気に営業しています。
こうした状況は、何を意味しているのでしょうか?
消費者が購入する店舗を選択する要因とは
ビジネスにおいて、ターゲットやニーズの多様化はもちろん必要です。
しかし「あの会社は何屋なのか」「何に強い会社か」ということが明確に伝わらない限り、消費者からは選ばれない店舗になります。企業や事業のブランディングにもつながっていきます。
消費者側も「なんでもある店」に行くのではなく、「カテゴリーに特化した品揃え豊富で、ちょっとお得なお店」を選択します。
そんななかで百貨店の“殿様商売”は、終わりを告げる時代に入っているのです。
消費者は、ある程度明確な目的意識を持って何かを購入する場合、その買い物する対象物の中で「何をどこで買うのか」を意識します。

その「何を」「どこで」の部分で、少なくとも上位3位ぐらいまでに入る会社や商品、サービスとして思い出されない店舗は、購入の選択肢として選ばれることはないでしょう。
総花的な品揃えや、強みや差別化を感じさせない商品やサービスをいくら作って並べたところで、購入者の選択肢には入りません。
経営者側は、このことを明確に意識する必要があります。
商品を売る側にとって最も大切なことは?
商品を売る側として大切なことは「何をもってお客様に記憶されたいか」ということです。この問いかけこそが、業界やカテゴリーにおいて記憶される企業となり、成長・発展していく大きなステップになります。
何屋かわからない「よろず屋」が、どれだけ商品やサービスを提供しても、どの消費者の記憶にも残りません。
販売する企業は、「商品自体に『強み』があるのか?」という問いに、常に答えていくことが重要です。
そのためには、商品の開発段階から「強み」を意識し続けることで、自社独自の力強いブランドを形成していかなければいけません。

つまり「強み」を生かした商品開発をしていくことが、顧客のココロに突き刺さる「競合他社を圧倒する差別化された強い商品・サービス・事業」である自社のカテゴリーキラー商品になり、群としてのカテゴリーブランドへと成長していくのです。
経営者の方は、今一度「何をもって消費者に記憶されたいか」と、ご自身の会社や事業へ向けて問いかけてみましょう。
この問いかけこそが「カテゴリーキラー」につながる考え方であり、自社のブランディングを推し進めるための「カテゴリーブランド」を創造していく大切なポイントになるのです。